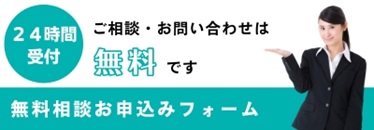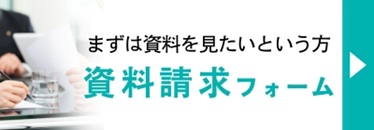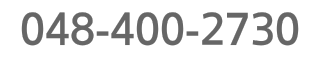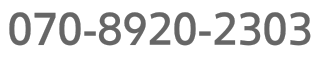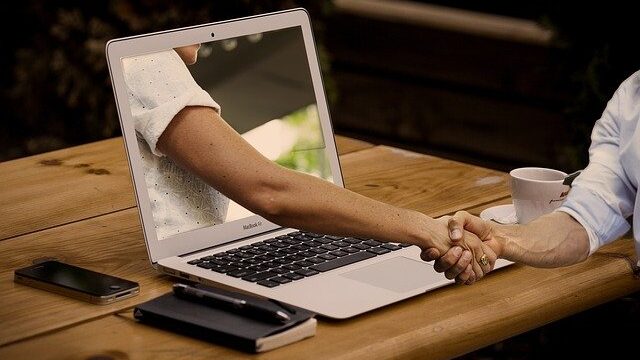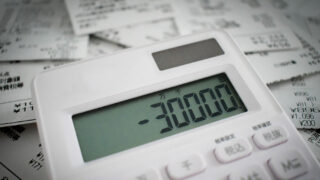2025年10月10日に公布された省令改正により、経営管理ビザの更新許可のハードルは以前とは比べ物にならないほど高くなりました。せっかく苦労して経営管理ビザを取得しても、更新申請が不許可になってしまえば全て水の泡です。
今後の「経営管理ビザの更新許可」を得るには、押さえておくべき2つの重要ポイントがあります。
【ポイント①】新しい要件を満たすこと(または、その見込みの証明)
【ポイント②】より厳格化された従来からの審査項目を満たすこと
この記事では、この2つのポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。
※経営管理ビザの正式な名称は在留資格「経営・管理」ですが、この記事では一般に知られている経営管理ビザという名称を使って解説します
【経営管理ビザ更新】新ルールの解説動画
【ポイント1】新しい要件を満たすこと(または、その見込みの証明)
猶予期間が設けられたものの、経営管理ビザの更新許可を得るには、今回の改正で設定された新しい要件を満たすことが原則必要です。
新要件と猶予期間について詳しく解説していきます。
【新要件】5つの項目を確認
省令改正により、2025年10月16日より、経営管理ビザの許可基準が大幅に引き上げられました。これは新規申請だけでなく、今後の更新申請においても適合が求められる重要な変更点です。
① 常勤職員の雇用について
申請者が経営する会社において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となりました。
(注)ここでいう「常勤職員」は、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」といった身分系の在留資格を持つ外国人に限られます。
② 資本金の額等について
事業の規模として、3,000万円以上の資本金等が必要になります。
(注)法人の場合は資本金の額または出資の総額を指します。個人事業主の場合は、事業のために投下されている総額(事務所経費、人件費、設備投資など)を指します。
③ 日本語能力について
申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(日本語能力試験N2相当など)を有することが必要です。
(注)この要件を満たすための「常勤職員」には、他の就労ビザで働く外国人も含まれます。
④ 経歴(学歴・職歴)について
申請者本人に、事業の経営または管理について3年以上の職歴、または経営管理に関連する修士号以上の学位が必要となります。
(注)この「3年以上の職歴」には、スタートアップビザ(特定活動)での起業準備活動の期間も含まれます。
⑤ 専門家による事業計画書の確認
事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった経営に関する専門家による「実現可能性がある」との確認を受けることが義務付けられました。
【超重要】3年間の経過措置と「見込み」の証明
「すでにビザを持っているのに、いきなりこの基準を満たすのは無理だ」と感じる方も多いでしょう。そのために、重要な経過措置が設けられています。
3年間の猶予期間(〜2028年10月16日)
すでにビザをお持ちの方がこの期間内に更新申請を行う場合、たとえ新基準を満たしていなくても、経営状況や「新基準に適合する見込み」等を踏まえて総合的に判断されます。
要注意:「見込み」がなければ不許可へ
この「適合する見込み」という部分が非常に重要です。これは「3年間は今のままで大丈夫」という意味ではなく、「3年後に向けて、新基準をクリアするための具体的な計画や行動を起こしているか」が審査されることを意味します。計画性がなければ更新は許可されません。
猶予期間中に取るべき対策
この3年間で、資本金を増やすための財務計画、人材の採用計画、日本語能力の向上計画などを立て、実行に移すことが求められます。
猶予期間終了後(2028年10月17日〜)
この日以降の更新は、原則として新基準への適合が必須となります。ただし、たとえ適合していなくても、経営状況が非常に良好で、納税義務も果たし、次回更新時までに適合する強い見込みがある場合は、例外的に許可される可能性も残されています。
【ポイント②】より厳格化された従来からの審査項目を満たすこと
次に、これまでも審査対象でしたが、今回の改正でより一層厳しく、かつ明確に審査されるようになった項目について解説します。これらは事業の実態そのものに関わる重要なポイントです。
【審査の厳格化】問われる「経営者としての実態」
事業内容と活動実態
ペーパーカンパニーではなく、きちんと事業活動が行われているかが審査されます。
特に、今回の改正で「業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、許可しない」と明確にガイドラインで示されました。これまでも事業の実態は審査の対象でしたが、今後は、例えば民泊運営の業務を業者に完全に丸投げしているようなケースは、「経営活動を行っていない」と判断されるリスクが格段に高まり、審査は一層厳しくなります。
事業所
事業を行うための事務所がきちんと確保されているかも審査のポイントです。改正後の規模に応じた経営活動を行うため、今まで一部のケースで認められていた自宅と事業所を兼ねることは、原則として認められなくなりました。また、新要件で常勤職員の雇用が義務化されたことに伴い、事業所の広さも考慮する必要があります。これまで多くの外国人経営者が利用してきた一人用のレンタルオフィスでは、雇用した職員の業務スペースが確保できないため、事業所として認められない可能性が非常に高くなります。
決算内容
直近の決算で債務超過に陥っていないことが一つの目安となります。債務超過とは会社の負債が資産を上回っている状態です。直近1期の赤字決算であれば許容されることが多いですが、債務超過をしている場合は、事業の継続性を合理的に説明する事業計画書等を提出し、審査官を納得させる必要があります。
公的義務の履行(納税・社会保険)
経営者個人の納税はもちろん、会社として各種税金や社会保険料をきちんと納付していることが絶対条件です。更新時には、労働保険、社会保険、国税(法人税、消費税等)、地方税(法人住民税等)の納付状況が厳しく確認されます。未納がある場合は更新が極めて難しくなります。
公的義務の履行(入管法上の届出)
また、意外に見落としがちなのが入管法上の届出義務の履行です。住居地の届出や、住所変更の届出、所属機関(会社)に関する届出等、出入国在留管理局への届出が滞りなく行われているかもしっかり確認されています。各種届出をうっかり忘れないように気をつけてください。
在留中の出国
在留期間中の出国についても、審査の考え方が大きく変わりました。
これまでは、①会社の経営が健全で、②納税義務も果たされていれば、経営者の長期出国が直接的な不許可理由になることは少ない傾向にありました。しかし、今回の改正で「正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、活動実態がないものとして更新を認めない」と明確化されました。これにより、今後は事業が順調でも、経営者自身が日本に滞在し、経営活動を行っている実態がなければ、更新は極めて難しくなります。
在留期間更新許可申請の必要書類(カテゴリー3の例)
これらの条件を満たしていることを証明するために、以下の書類が必要となります。
1.基本書類
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
- パスポート及び在留カード(申請時に提示)
2.会社の基本情報・決算に関する書類
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 直近の年度の決算文書の写し
- 法人の登記事項証明書の写し(該当する場合)
3.新要件・活動実態に関する書類
- 事業に必要な許認可の取得等を証明する資料(許可書等の写し)
- 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする資料
- 日本語能力を明らかにする資料
- 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書
4.納税・公租公課に関する書類
- (申請者個人の)住民税の課税・納税証明書
- (所属機関の)公租公課の履行状況を明らかにする資料(労働・社会保険の納付状況、各種国税・地方税の納税証明書など)
最後に
経営管理ビザの更新は、在留期間中の事業運営が適正であったかを総合的に判断される場です。特に2025年の改正以降は、提出書類も増え、事業の実態そのものがより詳細に審査されるようになりました。
日頃から健全な会社運営を心がけ、納税等の義務をきちんと果たしていくことが、スムーズな更新への一番の近道です。書類の準備やご自身の状況に少しでも不安がある場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。