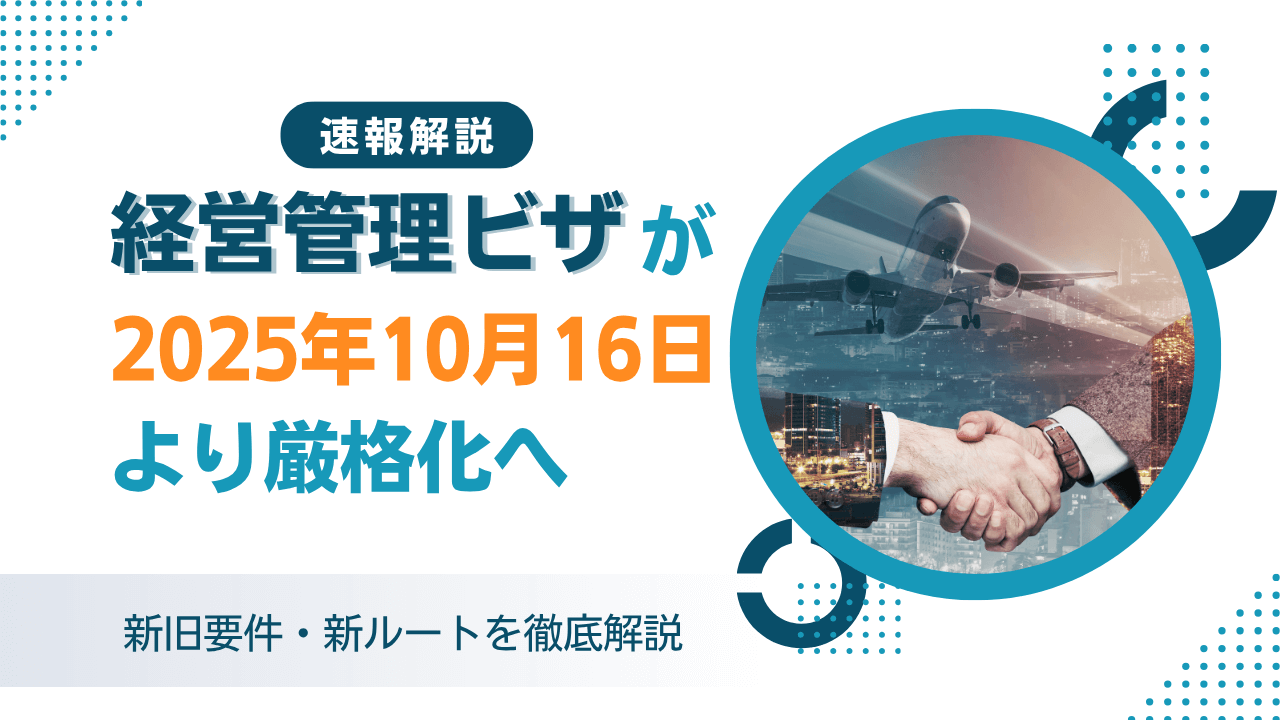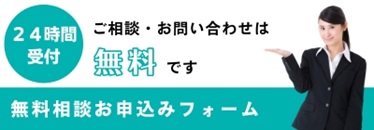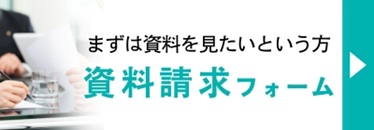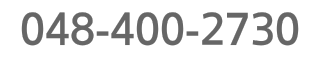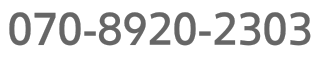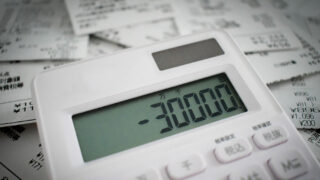2025年10月10日、在留資格「経営・管理」に関する基準を改正する省令が公布されました。日本での起業を目指す外国人の方々にとって、今後の計画に極めて大きな影響を与える内容となります。
今回の改正では、以前から議論されていた要件の厳格化に加え、最終的に日本語能力要件が追加されることが確定しました。
本記事では、公布された省令と出入国在留管理庁が発表したガイドラインに基づき、以下の4つのポイントを分かりやすく解説します。
- 【完全確定】新しいルールは何が変わるのか?
- 【駆け込み申請】施行日前の申請はどうなる?
- 【超重要】すでに経営管理ビザを持っている人の更新は?
- 【新たな王道】「スタートアップビザ(2年)」から「経営・管理」ビザへ
※この記事では、在留資格「経営・管理」をわかりやすくるすため、「経営管理ビザ」と表現して記載しております。
新要件の解説動画
1.【完全確定】新しいルールは何が変わるのか?
今回の改正で、経営管理ビザの許可基準は大幅に見直されました。出入国在留管理庁の発表によると、主に以下の5つの点で要件が厳格化されます。
改正内容の比較
| 項目 | 現行ルール | 新ルール(2025年10月16日〜) |
| ① 資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
| ② 経営者の経歴・学歴 | 特になし | 3年以上の経営・管理経験 または 関連分野の修士号以上の学位が必要 |
| ③ 職員の雇用義務 | 義務なし(資本金の代替要件として2人以上の雇用) | 1人以上の常勤職員の雇用が義務 |
| ④ 日本語能力 | 特になし | 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること |
| ⑤ 専門家による確認 | 特になし | 新規事業計画について専門家の確認が義務付けられる |
各ポイントの詳細解説
- ① 資本金・出資総額
事業規模の基準が、現行の6倍となる3,000万円に引き上げられます。
- ② 経営者の経歴・学歴
申請者本人に、経営者としての客観的な能力証明が求められます。「3年以上の経営・管理経験」には、在留資格「特定活動」で行う起業準備活動も含まれます。(※この点は後ほど詳しく解説します)
- ③ 職員の雇用義務
資本金要件とは別に、1名以上の常勤職員の雇用が必須となります。この「常勤職員」は、原則として日本人、特別永住者、または「永住者」などの身分系在留資格を持つ人に限られます。
- ④ 日本語能力
申請者本人、または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(CEFR B2相当、日本語能力試験N2などが想定)を持つ必要があります。なお、この日本語能力要件を満たすための「常勤職員」には、他の就労ビザで働く外国人も含まれるとされています。
- ⑤ 専門家による事業計画の確認
事業計画の実現可能性を客観的に示すため、経営に関する専門知識を持つ者(中小企業診断士など)による確認が義務化されます(上場企業規模などは除く)。
【重要】問われる「経営者としての活動実態」
上記の要件変更に加え、今回の改正の根本には、「事業への実質的な関与」を厳しく問うという強い意志があります。
入管が公表したガイドラインでは、以下の2点が明確に示されました。これは、特に民泊運営のように業務を外部に委託するビジネスモデルに大きな影響を与えます。
- ① 業務委託と活動実態
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。
これは、清掃やゲスト対応といった日常業務のほぼ全てを代行業者に丸投げしているようなケースを指します。経営者自身がマーケティング戦略や収益改善などに主体的に関与している実態がなければ、「経営者」とは認められません。今後は、業者に丸投げするだけの事業計画では、新規取得も更新も極めて難しくなります。
- ② 在留中の出国
在留期間中、正当な理由なく⾧期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
これも業務委託型のビジネスで起こりがちな問題です。運営を業者に任せ、経営者本人はほとんど日本に滞在しない、という「幽霊経営者」のような状態では、活動実態がないと判断されます。ビジネス上の出張など正当な理由なく長期間日本を離れていた場合、更新は認められません。
2.【駆け込み申請】施行日前の申請はどうなる?
新しいルールは2025年10月16日から施行されますが、それまでに申請を行う場合は、経過措置として現行のルールが適用されます。
- 申請期限
2025年10月15日までに申請を行えば、改正前の基準で審査されます。
- 認定証明書(COE)を既にお持ちの方
現行ルールで交付された認定証明書(COE)をお持ちの場合、その交付日から3ヶ月以内に日本へ入国(上陸申請)すれば問題ありません。
【重要】駆け込み申請に関する注意点
今回の厳格化は、制度の悪用を防ぐ目的もあります。
そのため、施行日直前のいわゆる「駆け込み申請」に対しては、審査がより一層厳しくなることが予想されます。たとえ現行基準を満たしていても、事業の実態や安定性・継続性について、これまで以上に慎重な審査が行われるでしょう。形式を整えただけの事業計画では不許可となるリスクがあるため、十分な準備が不可欠です。
3.【超重要】すでに経営管理ビザを持っている人の更新は?
既に経営管理ビザで活動している方の更新申請については、急激な変化を避けるための経過措置が設けられています。
3年間の猶予期間(〜2028年10月16日)
施行日から3年後、つまり2028年10月16日までに行う更新申請については、たとえ新しい基準を満たしていなくても、直ちに不許可とはなりません。現在の経営状況や、将来的に新基準を満たす見込みなどを踏まえて総合的に判断されます。
ただし、審査の過程で、経営の専門家による評価を受けた書類の提出を求められる場合があります。
猶予期間終了後(2028年10月17日〜)
3年の猶予期間が終了した後の更新申請は、原則として新しい基準を満たしている必要があります。
【例外措置】
ただし、猶予期間終了後も、新基準を満たせない場合でも、以下の要件を満たしている場合は、許可される可能性が残されています。
- 経営状況が良好であること
- 法人税などの納税義務を適切に履行していること
- 次回の更新申請時までに新基準を満たす見込みがあること
これらの要素を総合的に考慮し、最終的な判断が下されることになります。
4.【新たな王道】「スタートアップビザ(2年)」から「経営管理」ビザへ
さて、新しい「経営管理」ビザの要件、特に「3年以上の経営・管理経験」は非常に高いハードルです。
しかし、これをクリアするための新たな主要ルートとして注目されるのが、在留資格「特定活動」、通称「スタートアップビザ」です。
なぜ今までスタートアップビザは使われなかったのか?
スタートアップビザは、日本で起業準備をするために最長2年間滞在できる制度です。しかし、取得には地方公共団体などの事前審査が必要でした。これまでは「経営・管理」ビザのハードルが低かったため、わざわざ手間のかかるスタートアップビザを選択するメリットが乏しく、ほとんど利用されていませんでした。
なぜ今後、スタートアップビザが重要になるのか?
状況は一変します。新しい経営管理ビザの要件を、日本に基盤のない外国人が最初から満たすのは極めて困難です。
そこで、スタートアップビザが次のような役割を果たします。
- 「経営・管理経験」としてカウントされる
今回の改正で最も重要な点は、スタートアップビザで活動した期間が、「3年以上の経営・管理経験」の一部として認められることです。 - 段階的なアプローチが可能になる
最初から3,000万円の資本金や経営経験がなくても、まずは実現可能な事業計画でスタートアップビザを取得し、日本で活動しながら「経営・管理」ビザの要件を整えていく、という段階的なステップが踏めるようになります。
今後の起業ルート(想定)
- 【ステップ1】 事業計画を地方自治体等に提出し、スタートアップビザ(最長2年)を取得。
- 【ステップ2】 日本に滞在し、法人設立、資金調達、人材確保などの起業準備活動を行う(この期間が経営経験となる)。
- 【ステップ3】 準備が整い次第、「経営・管理」ビザへの変更申請を行う。
このように、これまで活用されてこなかったスタートアップビザが、今後は日本で起業を目指す外国人にとって、実質的な準備期間として、また経営経験を積むための重要な制度として広く使われることが想定されます。
まとめ
今回の経営管理ビザの改正は、単なる要件の引き上げにとどまらず、制度のあり方そのものを大きく転換させるものです。
最後に、重要なポイントを改めて整理します。
- 新規申請は大幅に厳格化
2025年10月16日以降、資本金3,000万円、経営経験3年以上など、極めて高いハードルが設けられます。また、事業運営を業者に丸投げするような「名ばかり経営者」は、活動実態がないと見なされ許可されません。 - 駆け込み申請は可能だが要注意
10月15日までに申請すれば旧基準が適用されますが、事業の実態については通常以上に厳しく審査されることが予想されます。 - 更新には3年間の猶予期間
すでにビザをお持ちの方は、2028年10月16日までは経過措置が適用されます。ただし、それ以降は原則として新基準を満たす必要があります。 - スタートアップビザが新ルートに
今後は、まず「スタートアップビザ」で日本での活動実績と経営経験を積み、その後「経営・管理」ビザへ移行するというステップが、外国人起業家の新たな王道ルートとなるでしょう。
今回の改正は、日本が外国人経営者を「量より質」で評価していくという明確なメッセージです。これから日本で起業を考えている方は、ご自身の状況と照らし合わせ、どのルートを選択すべきか、専門家も交えて慎重に検討することをお勧めします。